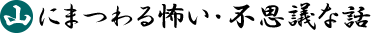あっさりと結界を破って俺の方へ 進入してくる虫がいた
2016/01/19
野営することがほとんどだ
そして野営する場合、必ず自分が寝るスペースを三ヒロ半確保し
以下の呪文を唱え、結界を張るようにしている
(「ナムアミダブツ、アボラウンキンソワカ」を三回)
ある日いつものように野営を行い、たき火を見ながら
うとうとしていると、あっさりと結界を破って俺の方へ
進入してくる虫がいた
(つづく)
しかしその虫が放つ”妖気”は尋常ではなかった
その証拠に、俺の目の前のたき火の炎が烈しく
揺れているのだ!ほぼ無風にもかかわらず・・・
そう考えている内にも虫は俺の手元まですでに来ていた
”うおっ!”とおびえつつ、俺はその虫を指ではじいた。
するとどうしたことだ?
その虫は先ほどより一回りから二回り大きくなって
また俺の方へテクテク歩いてきているではないか!
(つづく)
”なんだ一体・・・”と考える暇もなかった。
その虫は先ほどより大きくなっているだけではなく
歩いてくるスピードも先ほどより増している。
その虫が座っている俺の足下に触れた瞬間、
俺は登山靴で思いっきり、ぐりぐりと踏みつけた。
普段は無為な殺生はしない俺だが、かなりの恐怖心
に煽られて、ついついそうしてしまった。
しかしそんな自分の愚考を悔いてる間もなく、
その虫は俺の脚の下で土に埋もれることなく
丸石のように固く大きくなっていた
それは目測ではあるが、ネズミくらいはあったのだ!
(つづく)
すっかりおびえきった俺は、やおらそのネズミくらいの大きさになった虫を掴み、
林道対面側のガレキ谷へ向かってブン投げた。
しかし、その虫を投げることに夢中になり、結界解除の呪文を唱えることなく
俺は自ら結界の外へ脚を踏み出してしまっていたのだ・・・。
すっかり気が動転した俺はすぐにこの場をはなれるべくたき火の処理にあたった。
しかしそれは起こった。
背中越しに、先ほどの”妖気”を感じ取った。気の大きさも先ほど以上だ。
しかもこちらへ向かってくるスピードの速さは、その駆動音からして尋常ではない!
直後、俺は振り返りざまに、迫り来る虫の大きさに腰を抜かした!
柴犬の成犬程度はあろうかという大きさを持った虫が、ゴキブリを
数倍早くしたスピードで俺の方へ向かってきていた・・・。
(つづく)
もはや一刻の猶予もならなかった。
しかし対策は直ぐにひらめいていた
「衝撃を与えると大きくなる・・・それなら火にくべてしまえばいいじゃないか!
ザックはすでに背負っている。残るはたき火処理だけだが、もうかまっては居られない。」
一瞬の思考でそう判断した俺は、俺の足下へ向かってきたその虫を拾い上げ、
たき火に向かって叩き付けた。
”バチバチバチ!!”という轟音と共に、その虫の焼け焦げる音が山中にこだました。
俺はほっとして、後も振り返らず、出発点の営林所へ向けて小走りに山を下った。
”たき火は明日処理しにくればいいか。。。”
などと暢気に考えつつ・・・
(つづく)
営林所まで後数キロと行った地点で俺は小休止を取った。
昨年の登山でけが人をボッカしたときに痛めた左膝にかなりの
痛みが走っていたからだ。
水を飲みながらも俺は、周囲の様子を丹念に伺っていた。
今来た林道を虎視すると、何かが走ってくるのが見えた。
しかしそれは、無灯火の車のようにも見えるが、大和牛に
見えなくもない大きさだった。
その刹那、俺の首から下がっている数珠がすべて割れ落ちた。
俺は震え上がり、ザックをその場へ捨て、全速で山を駆け下りた。
もう確認するまでもない。間違いなく、あの虫でることを確信したのだ。
今まで山を味方のように、アル意味、俺をいやしてくれるカウンセラーのように
感じていた自然が、すべて俺を敵視しているかのような錯覚に襲われた。
振り返る余裕もなく、俺は営林所を目指した。
あの虫がすぐ背後にいるような錯覚にも捕われたが、それは山の妖気のような
気もしていた。
走りながらも、俺はすでに気を失いかけていた。
”どうせ殺されるなら気を失った方が楽だろうしな・・・”などと考えつつ
俺は道ばたへ倒れ込んだようだった。実は覚えていないのである。
どれだけ時間がたったのか、俺は林道の途中で倒れていたらしく
営林所の見回り車によって、起こされた。
(つづく)
営林署員に担がれて、おれは後部座席に放り込まれ、
ようやく一息入れることが出来た。
呆然としながらも、なぜ俺を捜しに来たのか、その職員にたずねてみた。
その内容を聞いて俺は愕然とした。
「あんたが現れたんだよ。よくあるんだそういったことが山にはさ~。
ドアのところに朝見たあんたの顔が、ぼーっと浮いていて、直ぐ消えたから
やべーと思ってすぐ車を走らせたんだよぉ~!」
車が到着する時間を考え合わせてみても、きっと俺の数珠が割れ落ちた
頃のことだろう。いや、勝手にそう願っていた。
別にあの虫の話をすることもなく、白々と明けゆく山裾を見ていた。
それ以後、二度と山には入っていない。
(終わり)