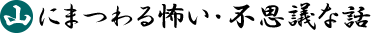近衛の舎人、常陸の国の山中にして歌を詠ひて死ぬる語
今は昔、ある所に近衛の舎人(近衛府の下級職員)が居ました。
神楽舎人なので、歌の上手でした。
ある時、舎人は仕事で東国に行くことになりました。
陸奥の国より、常陸の国へ超える山は「焼山の関」といって、とても深い山でしたが、そこを通る事になりました。
その山を通る時に、舎人は馬の上でウツラウツラとしておりました。
しばらくしてハッと気付き
「ここは常陸の国だろうか。随分と遠くまで来てしまったなぁ」
と思い、心細くなってしまいました。
そこで、拍子を打って「常陸歌」という歌を歌う事にしました。
2、3べん繰り返し歌った頃に、とても深い山奥から声が聞こえてきました。
「ああ、おもしろい」
その声は、とても恐ろしい声で、手を打って喜んでいるのです。
舎人は馬を止めて
「今のは誰が言った?」
と従者に聞きました。
従者は
「誰が言ったとは?何も聞こえませんでしたが…」
と言います。
舎人は頭の毛が太るような恐ろしさを感じて、その場を立ち去りました。
さて少し後、この舎人は気分が悪くなった後に、病気になってしまいました。
従者たちは、これはおかしいと思いましたが
その夜、舎人は宿で寝たまま、死んでしまいました。
山中では、歌を歌ってはいけません。
山神が歌を目出て、その人を引き留めてしまうでしょうから…。
常陸の国の歌だったので、その国の神が聞き、舎人を引き留めたのでしょう。
従者たちは、驚き嘆きながらも、なんとかして京に上りこの話を語りました。
これを聞いて、このように語り伝えられているという事です。
出典:今昔物語集