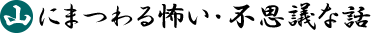酔いがかなり回り始めた頃、淵の対岸に白いモノが現れた
2016/02/11
インドは非常に好きな国だが、やはり日本が落ち着く。
俺はさすがに疲れた精神と肉体を癒すため、
出張中に溜まった代休をフルに」使ってとある高山の奥深くへ釣行した。
インドでもいくつかの山に登ったり、カシミール地方の高山地帯なんかにも
行ったが(ゲリラに戦々恐々だったが)、やはり日本の山は良い。
自分自身の心の中に帰れたような気さえする。
入山して二日目、深い淵で五十センチ越えの大岩魚を初め、
尺上のモノを中心に7本ほど上げてから
淵のほとりでツェルトを張り、飯を炊き味噌汁を作り岩魚を捌いて刺身にし、
男山で骨酒を拵えてちびちび飲っていると辺りが暗くなり始めて良い感じになって来た。
夜も更け始め、酔いがかなり回り始めた頃、淵の対岸に白いモノが現れた。
それが、白い着物を着た女だと認識するのに何秒かかったろうか。
その女は、淵を廻りながら俺に向かって歩いてくる。こんな山奥に何故そんなモノが?
酔いは一気に覚め、ハーケンを探して荷物に手を伸ばした。
瞬間、その女の顔が記憶を過る。
長く艶やかな黒髪、薄い眉、切れ長の目、赤く小さな唇、尖った顎。
ぞくっとする程の整った大人の顔立ちと、少女のあどけなさを併せ持っている。
「お前は…」思わず声が出てしまったとき、彼女の名を想い出した。
「おりょう…か?」
今年の渓流釣り解禁直後に山に篭った時、飯を振舞ってあげた礼に、
笹の香りのする美酒と美しい髪飾りを置いて姿を消した不可思議な男女。
男をごろう、女はおりょうと言った。
女は嬉しそうに微笑むと、小走りに俺の傍へやって来た。
前回会ったときと同じ様に、言葉は全く発さない。
立ち上がりかけた俺の首筋に噛付くように女は抱き付いて来た。
俺は女を抱き止めながら後ろ向きに転がってしまう。
彼女の髪からは、以前に嗅いだ若葉の香りではなく、甘やかな華の香りがした。
おりょうの軽い身体を抱きとめたまま天を仰いだ俺の目に、
俺の顔を覗く髭だらけの顔が映った。
「久しぶりですなあ。」
「ごろうさん、か…?」
俺が呟く様に声を発すると
「いやあ、覚えていてくれましたか。嬉しいですなあ」と彼が返す。
俺はおりょうに抱きつかれたまま身を起こした。
おりょうは俺の膝に乗ったまま俺の顔をじっと見つめている。
ふ、と彼女と目を合わせたら、
その漆黒の瞳の中に吸い込まれそうな感覚に包まれた。
いつの間にか、ごろうが俺の対面に座って竹水筒を差し出している。
俺は自然にそれを受け取り、口に含んだ。笹の爽やかな香りが口に広がる。
俺は、手元にあった骨酒を彼に渡す。彼も旨そうに骨酒を飲み干した。
そのまま一時ほど、何も喋らずにごろうと俺は岩魚をつまみに酒を酌み交わし、
おりょうは飯と焼いた岩魚を俺の膝の上でもぐもぐと食べていた。
ごろうからもらった一つ目の竹水筒が空になったとき、
「あんた、山が好きかね。」とごろうが俺に新しい竹水筒を渡しながら訊いて来た。
俺はごろうの竹コップに一升瓶から男山を注ぎながら、
「ああ、大好きですね。」と答えた。
「そうかね…」ごろうは呟くように言うと、また黙ってしまった。
おりょうは飯を食い終わり、胸元から取り出した小さな竹筒を口に含んでいる。
その竹筒から、桑の実のような甘い香りが漂ってきた。
「あんた、女房は居るのかね?」ごろうが唐突に聞いてきた。
おりょうがビクッと肉体を強張らせる感覚が伝わってきた。
「いや、居ない。独りもんですよ。」
あふう、とおりょうの唇から嘆息が出て、強張った肉体が弛緩する。
おりょうが俺の顔を見つめている視線を感じるが、
何故か怖くて彼女の顔を見れなかった。
「おりょうは次の満月に奥羽のおじきの総領息子へ嫁ぐんですわ。」
おりょうが俺にギュッと抱き付きながら身体を強張らせる。
意外なほどにたっぷりとした量感を持つ胸を押し付けられて、
俺の心臓の脈も早まってしまった。
「それは…目出度い…のかな…?」
なんだか間抜けな答えを返してしまう俺。
「はああ!?」
あまりにも唐突な問いに思わず度肝を抜かれる俺。
おりょうの唇が俺の首筋に吸い付く感触を感じ、我に返った。
「可愛い…と思いますよ。」首筋を強く吸われ、そして舌が這う感触。
痺れる様な感覚がする。
「あんたは、街に帰りたいと思うかね?」
「俺…は、山が好きだ…けれど、街を捨てることは…出来ない…と思う…。痛っ!」
鋭い痛みが首筋に走った。「おりょう!」ごろうが一喝した。
ビクッと身体を震わせて俺の首筋から唇を離すおりょう。
彼女の顔を見ると、唇から血を流している。
いや、その血は俺の首筋から出たものだった。
「……」おりょうが俺の目を見詰め、俺の目もおりょうの瞳に吸い付けられていた。
唐突におりょうの瞳に涙が溢れ、俺の唇におりょうの唇が重なった。
おりょうの舌が俺の口の中に入ってくる。甘い林檎のような香りと、
鉄錆のような俺の血の味が混ざっていた。
どれほどそのままで居ただろうか。おりょうは俺から唇を離すと、
もう一度ぎゅう、と抱き付いてきた。
「さよなら…。」鈴の音が鳴るような声がおりょうの口から漏れる。
呆然とする俺の目の前でごろうも立ち上がった。
「あんたなら、おりょうの良人に相応しいと思ったが…やはり難しいかのう。」
「ごろうさん…俺は…」俺は何を言いたいのだろうか、いや、どうしたいのだろうか。
その時は全く解らなかった。
「あんたが山に来続けるならば、またいつか逢う機会もあるじゃろう。達者でな」
俺は、二人が山の闇の中へ消えていくのを立ち上がることも出来ずに見送るだけだった。
淵の向こう側で、おりょうが一度だけこっちを振り返るのが見えた。
翌朝、俺はツェルトの中で目が覚めた。
いつ、どうやって寝たのかも覚えていない。
「昨夜の事は夢…なのか?」
独り言を呟きながら外に這い出し、淵の水に映る自分を見る。
首筋に、噛み千切られたような傷跡が残っていた。
その傷跡を見付けた途端、涙が滝のように溢れだした。
なぜか胸が締め付けられるように痛み、俺は独り咽び泣いた。